連続講座「2025年度・レジリエンス━破綻と回復の境界」第1回講義レポート
京都大学経営管理大学院レジリエンス経営科学研究寄附講座では、昨年度に引き続き、レジリエンスについて考える連続講座を開催します。今年度も各講義100人を超える方々からのお申し込みをいただき、改めて非常に多くの方が関心を寄せているテーマであることを再確認いたしました。ご参加できない方やもう一度講義を見直したい方に向けて、毎回の講義動画を公開いたします。
浜崎特定准教授による第一回の講義では、最初にレジリエンスの意味を概説した後、21世紀のポストリベラリズム社会がもたらす危機はどのようなものか、そしてそれを克服するヒントとなる、オープンダイアローグの考え方について述べられました。さらに、日本人へと視点を移し、いかにして自然な生き方を手に入れることができるのか、九鬼周造の哲学を援用しながら解説されました。
【開催概要】
日時: 2025 年 9 月 20 日(土)16:00-18:00
登壇者: 浜崎 洋介(京都大学経営管理大学院レジリエンス経営科学研究寄附講座特定准教授、文芸批評家)
場所:京都大学吉田キャンパス 総合研究2号館1階 講義室1
テーマ: 「いき」とレジリエンス―「おのずから」と「みずから」の関係をめぐって
レジリエンスの定義:竹のような「しなやかさ」
浜崎洋介准教授は、講義の冒頭で「レジリエンスとは竹のようなしなやかさである」と定義しています。工学では外圧による歪みに耐えて復元する力として使われますが、准教授はそれを単なる「強さ」ではなく、「時間をかけて回復する生命的な力」として捉えます。破壊や損傷の後に再び立ち上がる力には、時間的な生成、すなわち生命の流れが内在しているというのです。
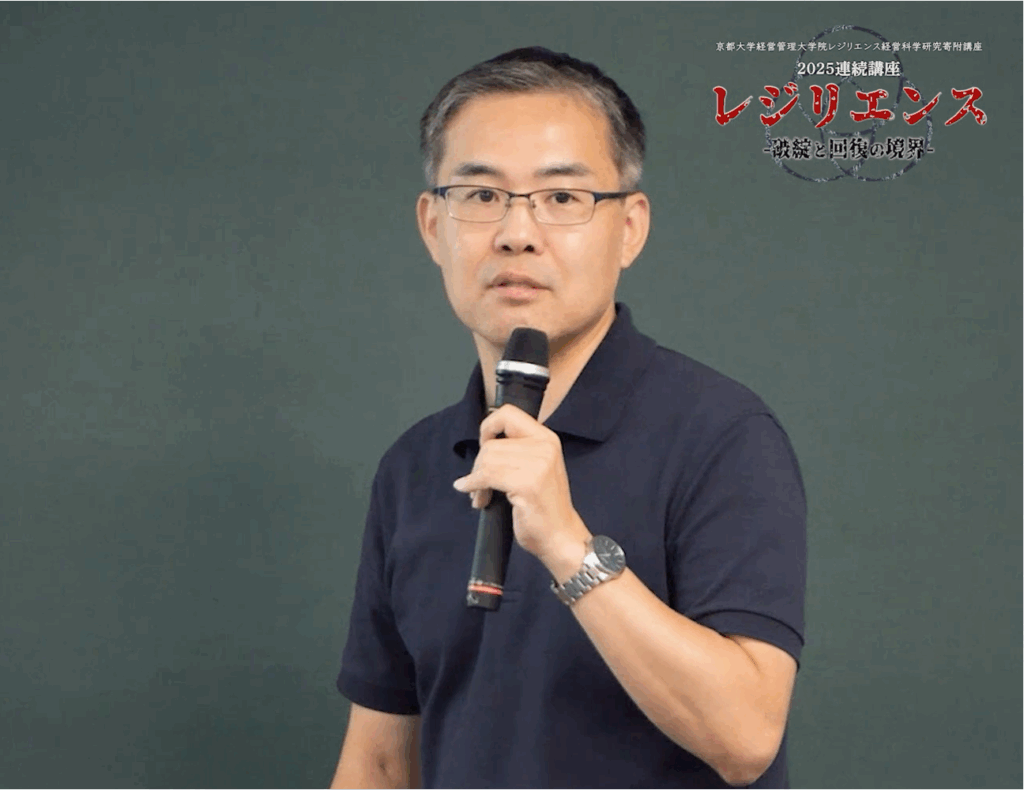
そのため、レジリエンスを「堅牢性(ロバストネス)」と訳すのは誤りであり、むしろ「しなやかさ」や「弾力性」と表現すべきだと述べます。「ポキッと折れてしまえばそれで終わりだが、竹のようにしなって元に戻る」と例え、心理学や生態学の文脈においてもこの概念が重要であると説きました 。
加えて、レジリエンスを支える条件として「多様性と冗長性」「モジュール性」「柔軟なフィードバック」という三つの要素を挙げます。これは、特定の価値観や構造に依存せず、複数の関係や可能性を保ち続ける力のことを指しています。選択と集中ではなく、あえて流動性を許容すること。そこに人間的な回復力の基盤があると強調しました。
現代社会の危機:リベラリズムが生んだ「硬直化」
続いて、現代社会の危機を「リベラリズムの硬直化」として分析します。アメリカの政治思想家パトリック・デニーンの議論を引用し、「リベラリズムは失敗した。それは実現できなかったからではなく、成功したために失敗した」と紹介しました。さらに、フランスの政治思想家であるアレクシ・ド・トクヴィルの論を用いながら、リベラリズムが徹底されると、自由と平等の追求が社会的連帯を解体し、結果的に個人を孤立へと導く――その構造的矛盾を指摘しています 。
リベラリズムによって身分や権力に基づいた制度や権威が「人為的な虚構」として相対化されることで、人々は自分を守ってくれるものを求めて再び国家や多数派に依存するようになる。こうして「自由を守るはずの思想」が「多数者の専制」へと転化するという皮肉が生まれると言うのです。
浜崎准教授は、コロナ禍で「感染予防」という一つの正義に社会全体が収斂し、異論を封じる空気が形成されたことを例に挙げ、「リベラリズムが生んだ新しい同調圧力」であると批判しました。自由を追い求めた結果、硬直化して、逆に社会の自由が失われていく。このパラドックスこそが現代の危機だと述べています。
その上で、個人を孤立させないために「中間共同体」の存在が不可欠だと語りました。家族、地域、宗教的結社など、国家でも個人でもない「間(あいだ)」にあるつながりを作る。そこには、目的や成果を超えて「共にあること」そのものを価値とする関係性が生まれます。浜崎准教授はこれを「目的なき共同体」と呼び、現代におけるレジリエンスの基盤と位置づけました。
回復の方法:オープンダイアローグ
こうした「目的なき共同体」を体現する実践として、フィンランドの精神医療「オープンダイアローグ」が紹介されました。1980年代、西ラップランド地方のゲロプダス病院で生まれたこの手法は、薬物投与や入院を最小限にし、患者・家族・医療者が対等に語り合うことを原則とします。
一般的な医療は、医師が上位に立ち、一方向的に治療方法を決定する構造が主流でしたが、オープンダイアローグは全員に「聞こえる場」で進みます。医師と看護師が患者の見えないところで、治療方針を決定するのではなく、患者の前で全員が意見を交わし、患者は「観察者」としてそのやりとりを聞きます 。
この「リフレクティング」と呼ばれる手法は、患者が自分に関する言葉を他者の声として聴き直す契機になります。これによって固定化された自己像がゆるみ、自分自身を捉えなすことができる回復のプロセスが始まるのです。
この仕組みを浜崎准教授は、対話そのものが治療であり、結論ではなく継続が目的であると説明しました。この「オープンダイアローグ」の思想的背景には、ロシアの文芸理論家ミハイル・バフチンの「ポリフォニー(多声性)」があると続けます。ポリフォニーとは、複数の声が同時に存在し、どれも絶対化されない状態を指します。この複数の声が響き合う開かれた対話空間が、実は人間を解放させるというのです。
対話には、あらかじめ目的や答えを設定しない勇気が必要です。偶然性に身を委ね、他者の言葉に揺さぶられながら関係を編み直していく。この「おのずから生まれる回復の力」が、浜崎准教授のいうレジリエンスに繋がっていきます。
日本的レジリエンス:「おのずから」と「みずから」の調和
講義の終盤では、こうした思想を日本的倫理の文脈に接続する試みが行われました。
ここで取り上げられたのが哲学者・九鬼周造です。九鬼は「粋(いき)」という美学概念を通して、日本の倫理や生のあり方を論じた人物でした。浜崎准教授は、九鬼が「生きていることそのものに開かれ、凝り固まらない態度」を「粋」と呼び、それを日本人が長年培ってきた生きる倫理としたと紹介しています。
その上で、九鬼の哲学の核心である「おのずから」と「みずから」の関係に着目します。「おのずから」を自然発生的な他力性、「みずから」を意志的な自力性として説明します。「他力だけでは依存に陥るが、自力だけでも限界に突き当たる」と述べ、どちらか一方に偏ると人間は不完全になるため、自力と他力の往還の中に人間の成熟があると指摘しました。
つまり、人は「みずから」を徹底したときに初めてその限界に気づき、「おのずから」に開かれる。その後、再び「みずから生きる」地点に戻ってくる――この循環こそが倫理の核心だといいます 。
この「おのずから」と「みずから」の調和は、まさにレジリエンスの本質であるというのです。意志と自然、計画と偶然、自己と他者のあいだに生まれる柔軟な関係。それは、竹のように風にしなりながらも根を張って立つ姿に重なります。
講義は、レジリエンスが単に外部の力に耐えることではなく、しなやかに回復し続ける「生きる」ことそのものの倫理であるという視座を示す形で締めくくられました。


