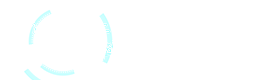連続講座「2024 年度・レジリエンス―⼈間と社会の強靭性を考える」第7回開催レポート
第7回「レジリエンス経営科学研究寄附講座」では、京都大学経営管理大学院の山田忠史教授が「持続可能なビジネスとIT―わが国の物流を題材として」について講義を行いました。交通計画・物流計画の専門家として長年研究に携わってきた山田教授が、最適化計算とAIの関係性、日本の物流が直面する課題、そしてデジタル技術を活用した持続可能な物流システムの構築について多角的に論じました。
近年、トラックドライバー不足や環境問題などの課題に直面する日本の物流業界。その一方で、IOT・ICT・ビッグデータ・AIといったデジタル技術が急速に進展しています。こうした状況の中で、単なる「言葉遊び」に終わらないデジタルトランスフォーメーションとは何か、そして真に持続可能な物流システムをどう構築すべきか――。山田教授は工学的視点とビジネス的視点を融合させながら、これからの物流の在り方を提示しました。
【開催概要】
日 時:2025年3月15日(土)16:00-18:00
登壇者:山田 忠史 京都大学経営管理大学院教授
テーマ:持続可能なビジネスとIT―わが国の物流を題材として
最適化計算とAIの本質
講義の冒頭、山田教授はまず自身の専門である交通計画・物流計画における最適化計算とAIの関係性について解説しました。「AIという言葉が一人歩きしている現状」に対して、AIの本質は「生物の進化や行動を模倣した計算方法の総称」であり、最適化アルゴリズムは、持続可能な都市交通物流システムの設計に応用されていると山田教授は語りました。

「とりあえずAIと言えば何とかなる」という安易な考え方ではなく、本質を理解した上で技術とビジネスを融合させるべきだと山田教授は強調します。「技術を真に理解して、それに基づいてビジネスを立ち上げるという『マネジメント・オン・テクノロジー』の発想が重要だ」と述べ、単なる「マネジメント・オブ・テクノロジー」との違いを明確にしました。
日本の物流が直面する課題
続いて、日本の物流業界が直面する深刻な課題としてトラックドライバー不足の問題が取り上げられました。山田教授が示したデータによれば、ドライバーの数は年々減少しており、全年代で減少傾向にあります。さらに、働き方改革による労働時間短縮も加わり、現在の物流システムの維持が困難になりつつあるのです。
この問題の背景には、1990年代の規制緩和があると指摘します。免許制から許可制への変更により物流業者数が急増した結果、過当競争が生じて運賃が下落。かつては全産業平均よりも高かったトラックドライバーの所得が徐々に低下し、「夢のない商売」になってしまったと分析しました。こうした状況に対して「外国人ドライバーの導入」という解決策が提案されることがありますが、給与水準の国際比較(日本の約400万円に対し米国では2,000万円超)や、言語の問題、高度な物流品質の維持、災害時の対応など多角的な観点から、真の解決にはならないと主張しました。
デジタル技術を活用した新たな物流システム
講義の後半では、デジタル技術を活用した新たな物流システムの可能性について議論が展開されました。まず、デジタイゼーション(電子化)、デジタライゼーション(デジタル化・IT化)、スマート化といった概念の違いを整理した上で、デジタルトランスフォーメーション(DX)は単なるデジタル化ではなく、社会や生活、産業、ビジネスのイノベーションが伴う変革であるべきだと山田教授は強調します。
そして、IOT(モノのインターネット)・ICT(人のネット化)・ビッグデータ・AIという一連の技術が物流にもたらす変革の可能性について語りました。特に注目すべきは「見える化」の実現です。データが取れることで物流の全体像が見えるようになり、部分最適ではなく全体最適、すなわち「ロジスティクス」が可能になるというのです。
この流れの中で登場したのが「フィジカルインターネット」の概念です。インターネットでは情報がどのような経路でやり取りされているかユーザーは気にしないように、物流においても「何で運ばれたか」ではなく「確実に届くか」だけを重視するシステムへの転換を目指しています。山田教授はこれが物流効率化の鍵となり、トラックドライバー不足の緩和や環境負荷の低減につながると説明しました。
レジリエンスと物流の未来
世界の IT 巨人が展開するプラットフォームビジネス(GAFA など)の成功モデルを解説しながら、山田教授は物流版の MaaS(Mobility as a Service)の可能性についても言及しました。交通分野を例に、「アプリを通じて様々な移動手段を選択・予約・決済できるシステム」としてのMaasが登場したように、物流においても輸送手段の最適な選択をアプリ上で一元管理する「物流 MaaS」が構想されています。
こうしたシステムが実現すれば、異なる物流業者間での貨物の共同輸送や、トラック以外の輸送手段(鉄道・船舶)の活用が進み、効率化とともにマルチモーダル化(複数の輸送手段の活用)が図れ、ドライバー不足の緩和・解消していくと説明します。特に災害時においては、普段から複数の輸送手段を活用しておくことが「レジリエンス(強靭性)」につながると強調しました。
講義の締めくくりとして、レジリエンスを「様々なリスク要因に対して、事前に予防策を講じ(頑健性)、事後においては迅速(時間的回復性)かつ効果的(性能的回復性)に回復できる能力」であると定義し、これを物流システムに適用する重要性を語りました。
さらに、「インフラとスープラの融合型ビジネスモデル」の必要性を訴えました。「スープラ」が上部構造、「インフラ」が下部構造を意味するように、AIやデジタル技術といった「スープラ」だけでなく、それを支える物理的な「インフラ」も不可欠であると主張します。「技術(スープラ)を活かすためには強靭な肉体(インフラ)が必要」であり、両者のバランスが取れた発展の重要性を訴えて講義を締めくくりました。
浜崎洋介特定准教授との対談が行われ、持続可能な物流システムの構築に向けた課題と展望について議論が深めます。

この第7回をもって、2024年度「レジリエンス――人間と社会の強靭性を考える」連続講座は終了となりました。全7回を通じて、多角的な視点から人と共同体のレジリエンス力を高めるヒントが提示され、自己と社会を理性的にとらえる力を育む機会となりました。